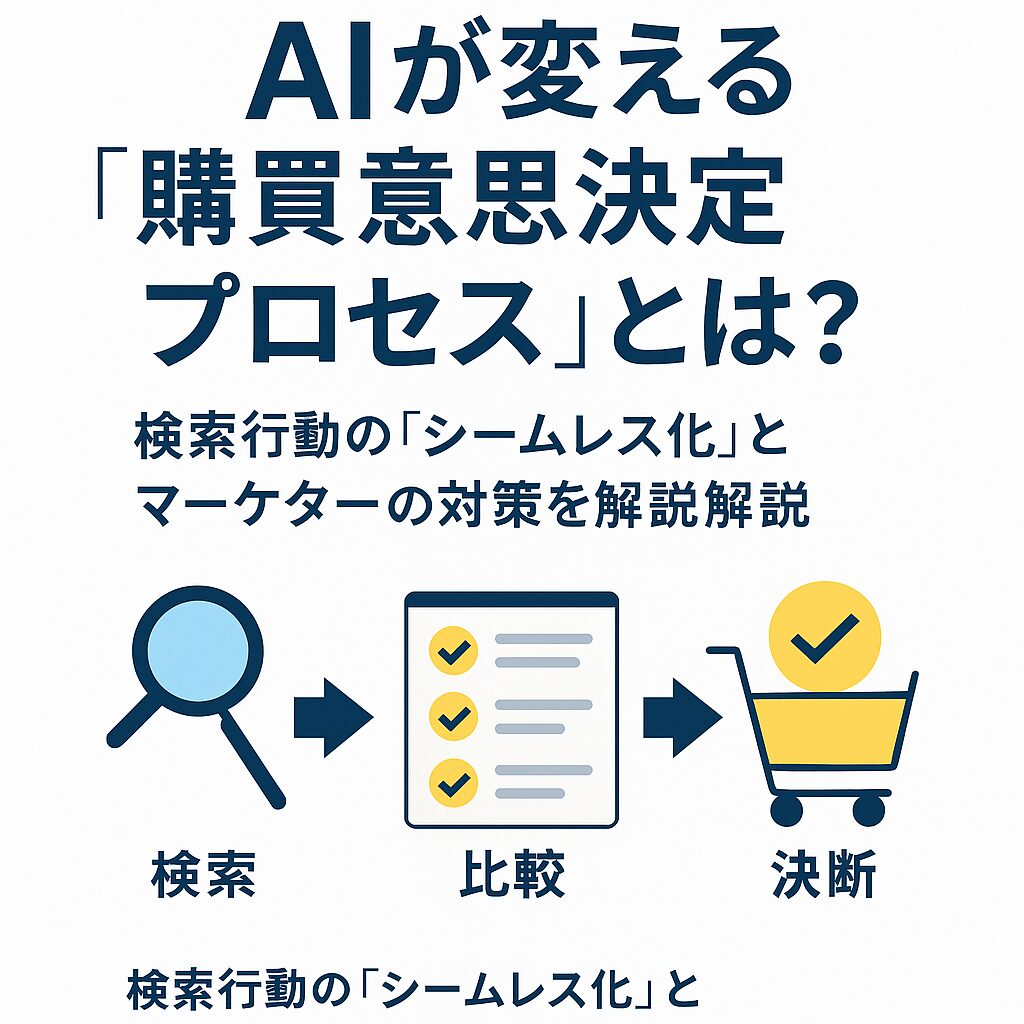「最近のAI(SGEなど)は、検索するだけですぐに比較表が出てきて、購入までスムーズになった…」
「AIが検索体験を変える中、自社のコンテンツは今後どうなるんだろう?」
企業のマーケティング担当者様なら、このような変化に期待と不安を感じているのではないでしょうか。
ユーザーが「検索」し、「比較」し、「決断」する——。
この一連の行動は、マーケティング用語で
「購買意思決定プロセス」と呼ばれます。
これまで分断されていたこのプロセスを、今まさにAIが「橋渡し」し、シームレスに変えようとしています。
この記事では、「購買意思決定プロセス」の基本から、AIがもたらす変化、そして私たちマーケターが今から準備すべきことまでを、分かりやすく解説します。
目次
1. 「購買意思決定プロセス」とは?
まず、この「購買意思決定プロセス」とは何か、基本をおさらいしましょう。
これは、消費者が特定の商品やサービスを認知してから、購入するまでにたどる心理的なステップをモデル化したものです。
1-1. マーケティングの基本:コトラーの5段階モデル
最も有名なモデルとして、経営学者のフィリップ・コトラーが提唱した「5段階モデル」があります。
| ①問題認識 | 「シャンプーがなくなりそう」「作業が重いから新しいPCが欲しい」など、ニーズや課題に気付く段階。 |
| ②情報探索 | 「どのシャンプーが人気?」「おすすめのPCは?」と、解決策の情報を探し始める段階。 |
| ③代替品評価 | 「A社のPCは軽いが値段が高い。B社は安いが重い…」と、集めた情報をもとに選択肢を比較・評価する段階。 |
| ④購買決定 | 「よし、デザインも良いA社のPCにしよう!」と、最も良いと判断した選択肢を購入する段階。 |
| ⑤購買後の行動 | 「買ってよかった!」「期待したほどではなかった…」と、購入した製品を評価し、次の行動(リピートや口コミ)に移る段階。 |
1-2. あなたの「検索→比較→決断」行動との一致点
このモデルに、冒頭の疑問を当てはめてみましょう。
「検索する」「見る」 → ② 情報探索
「比較する」 → ③ 代替品評価
「決める」 → ④ 購買決定
このように、私たちが日常的に検索エンジンで行っている行動は、まさに「購買意思決定プロセス」の核となる部分そのものだったのです。
2. AIが「購買意思決定プロセス」をどう変えるのか?
では、なぜ今AIがこの購買意思決定プロセスを「橋渡し」すると言われているのでしょうか?
それは、従来、このプロセスが「断片化(フラグメンテーション)」していたからです。
2-1. 従来:分断されていた「探索」と「評価」
これまでの私たちは、以下のようにアプリやサイトを何度も「移動」する必要がありました。
② 情報探索検索エンジンでキーワードを打ち、複数のブログやニュースサイトをタブで大量に開く。
③ 代替品評価別途、比較サイトに移動したり、自分でExcelに情報をまとめたりして比較する。
④ 購買決定ECサイト(Amazonや楽天など)に移動し直し、カートに入れて決済する。
このように、ステップごとに情報もツールも分断されていました。
2-2. AI時代:「シームレス化」する検索体験の例
しかし、生成AIは、この②情報探索、③代替品評価、④購買決定を、一つの画面や会話で「シームレス(継ぎ目なく)」に実行しようとしています。
<AIによる橋渡し(イメージ)>
あなた: 「軽くてバッテリーが持つ、15万円以下のノートPCを探して。A社とB社の違いも教えて」
AI: 「かしこまりました。条件に合うPCはこちらです。A社はデザイン性に優れ、B社は処理速度が速いのが特徴です。比較表はこちらです。[比較表を自動生成]…A社の製品を購入されますか?」
このように、AIが「検索」「見る」「比較」「決める」を一気にサポートすることで、私たちは面倒な「移動」や「情報の分断」から解放され、よりスムーズな体験が可能になります。
3. AI時代の変化にマーケターはどう対応すべきか?
この「シームレス化」は、マーケターにとって大きな変革を意味します。
AIがユーザーの行動を先回りしてサポートするなら、企業側(コンテンツ提供側)も、それに合わせた対策が必要です。
3-1. 対策1:検索意図の「先回り」と「網羅」
AIは、ユーザーの「情報探索(②)」の裏にある「代替品評価(③)」や「購買決定(④)」の意図まで先読みして回答を生成します。
これまでのSEO対策のように、「〇〇 おすすめ」という記事だけを用意しても、AIの回答(比較表など)の一部に使われるだけで、読者が自社サイトを訪れる理由が弱くなります。
これからは、「情報探索」から「購買決定」までを網羅するコンテンツが必要です。
例えば、単におすすめのPCを羅列するだけでなく、「AとBの比較(代替品評価)」や「こういう人にはAがおすすめ(購買決定の基準)」といった、プロセス全体をサポートする情報を1ページ、あるいはサイト全体で提供する視点が重要になります。
3-2. 対策2:AIの参照元となる「信頼性」と「体験談」の強化 (E-E-A-T)
AIはゼロから情報を生み出しているわけではなく、既存のWeb上の情報を参照・学習して回答を生成しています。
では、AIはどの情報を参照するのでしょうか?
それは、「信頼できる」と判断した情報です。
GoogleがWebサイトの品質評価基準として掲げる「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性が、AI時代にますます高まります。
AIでも生成できるような一般的な情報(「〇〇とは」など)の価値は相対的に低下します。
マーケターが注力すべきは、AIには真似できない、独自の価値です。
Experience(経験):
実際に製品を使った詳細なレビュー、導入した企業の一次情報。
Expertise(専門性):
専門家による深い洞察、独自のデータ分析。
Authoritativeness(権威性):
その分野の第一人者としての実績、公的機関からの引用。
Trustworthiness(信頼性):
運営者情報の明記、正確な情報提供。
これらの「信頼の証」が豊富なコンテンツこそが、AIの参照元として選ばれ、結果としてユーザーの「購買意思決定プロセス」に組み込まれるのです。
4. まとめ:AI時代の「購買意思決定」をリードするために
本記事のポイントをまとめます。
- ユーザーの「検索・比較・決断」という行動は、マーケティング用語で「購買意思決定プロセス」と呼ばれる。
- 従来、このプロセスはサイトの「移動」によって「断片化」していた。
- AIは、このプロセスを一つの画面で完結させる「シームレス化」を急速に進めている。
- マーケターは、「意図の先読み」と「E-E-A-T(特に独自の経験・専門性)」を強化したコンテンツで対応する必要がある。
AIによる検索体験の変化は、ユーザーの意思決定をよりスマートに、より速くするものです。
この変化を脅威ではなく「ユーザーにより早く、より良い価値を届けるチャンス」と捉え、信頼される情報発信を強化していきましょう。