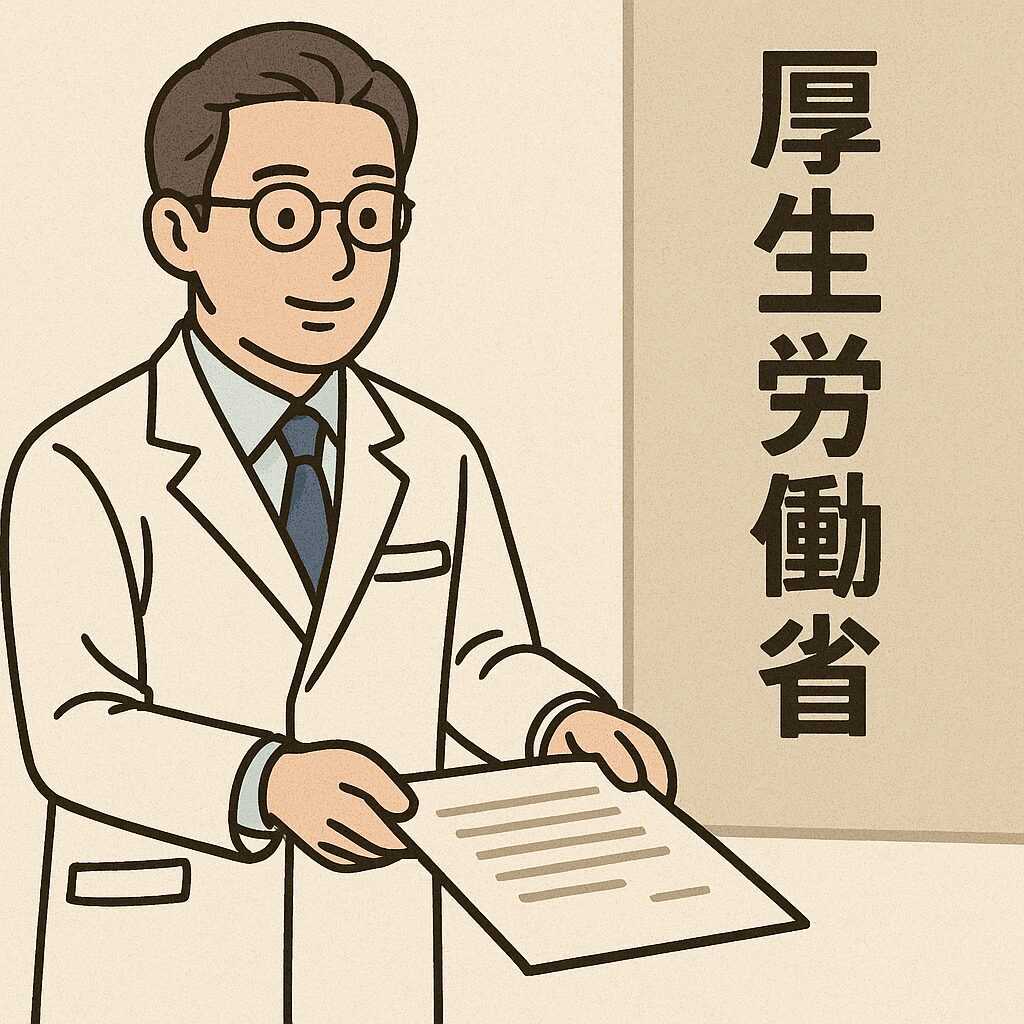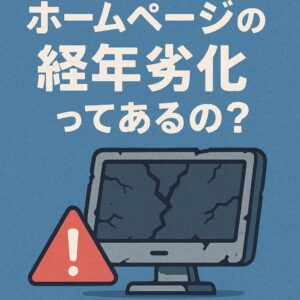1. 歯科医院診療報酬改定の目的
令和6年(2024年)6月1日に施行された診療報酬改定の目的は、
・患者さんの安全確保
・院内感染対策の強化
・ライフステージに応じた継続的な口腔管理の推進
・医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の促進などを
としています 。 (厚生労働省)。
この改定に伴い、特に「施設基準」に関して大きな見直しが行われました。
施設基準とは、特定の診療行為に対して高い診療報酬(加算)を算定するために、人員配置、設備、運用体制などについて定められた要件のことです。これを満たしていることを地方厚生(支)局(以下、厚生局)に届け出ることで、該当する加算を算定できるようになります。
今回の改定で特に影響の大きい施設基準の変更
「歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)」や「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」といった従来の基準が廃止・再編され、
「歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)」
「歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)」
「口腔管理体制強化加算(口管強)」
といった新しい基準が登場しました。
旧基準からスムーズに移行するステップを解説します
すでに旧基準の届出を行っていた歯科医院が、新しい基準へスムーズに移行するための「経過措置」について、何を、いつまでに、どのように厚生局へ提出(届出)する必要があるのかを解説します。
2. 経過措置とは? 対象となる歯科医院と重要な期限
今回の診療報酬改定では、従来の「外来環1」や「か強診」の基準を満たしていた歯科医院が、新しい基準(外安全1、外感染1、口管強)へ円滑に移行できるよう、「経過措置」が設けられています。
経過措置の対象となる歯科医院
原則として、令和6年(2024年)3月31日時点で、旧基準である「外来環1」または「か強診」の届出を行い、受理されていた歯科医院が、これらの基準に関する経過措置の対象となります 。
重要な点として、令和6年4月1日以降に旧基準の届出を行った(例えば、新規開業などで4月や5月に届出をした)歯科医院は、この特定の経過措置の対象とはなりません。 (参考:令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省)
※これらの医院は、令和6年6月1日から新しい基準の加算を算定したい場合、原則として令和6年6月3日(月)までに新しい基準を満たして届出を行う必要がありました。
経過措置期間中の「みなし認定」とは
経過措置の期間中、対象となる歯科医院は、新しい基準(外安全1、外感染1、口管強)の一部の要件について、まだ新しい届出を提出していなくても、基準を満たしているものとして「みなされる」(みなし認定)扱いを受けます。
これにより、令和6年6月1日以降も、直ちに加算の算定ができなくなる事態を避けることができていました。
ただし、「みなし認定」は全ての新要件を免除するものではない点に注意が必要です。
後述するように、特に口管強などでは、経過措置の対象外となる新しい要件も存在します。
最も重要な期限:令和7年(2025年)5月31日
この経過措置に関連する最も重要な期限は、
令和7年(2025年)5月31日(土)です。
この日までに、経過措置の対象となっていた歯科医院が、令和7年6月1日以降も引き続き外安全1、外感染1、または口管強の加算を算定したい場合には、
新しい基準の全ての要件を満たした上で、改めて厚生局に届出(再届出)を完了させる必要があります。
5月31日を過ぎると、「みなし認定」の効力は失われ、再届出がなければこれらの加算は算定できなくなります。
令和6年3月31日時点で外来環1・か強診を届け出ていた医院の多くにとっては、令和7年5月31日が再届出の最終期限となります。
期限を守らなかった場合
令和7年5月31日までに再届出を行わなかった場合、令和7年6月1日以降、外安全1、外感染1、口管強の加算は算定できなくなります。これは医院の収入に直接影響を与える可能性があります。
3. 主な施設基準の変更点:外来環1・か強診から新基準へ
今回の改定では、歯科医院にとって馴染みの深かった「外来環1」と「か強診」が廃止・再編されました。その背景と、新しく登場した基準の概要を見ていきましょう。
4. 新しい施設基準を満たすための具体的要件
令和7年5月31日の経過措置期限までに再届出を行うためには、新しい施設基準の全ての要件を満たす必要があります。
ここでは、外安全1、外感染1、口管強、そしてこれらと関連の深い歯初診の主な要件を解説します。
なお、施設基準の完全な詳細については、必ず厚生労働省が発表する最新の告示・通知原文をご確認ください(厚生労働省:令和6年度診療報酬改定について: )。
また、厚生局が提供する「施設基準届出チェックリスト」を活用することも、要件の確認漏れを防ぐ上で非常に有効です 。
施設基準変更の背景
外来環1 → 外安全1 + 外感染1
- 従来の「外来環1」は、医療安全対策と感染防止対策の両方を含む基準でした。これを「外安全1(医療安全対策)」と「外感染1(感染対策)」に分割することで、それぞれの対策をより明確に評価し、強化する狙いがあります。
特に感染対策については、より多くの歯科医院が取り組みやすいように要件が一部見直された側面もあります。これは、患者安全と感染制御の重要性がますます高まっている社会情勢を反映したものと言えます。
か強診 → 口管強
- 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」という名称は、患者さんや歯科医師自身にとっても「普段通っている歯科医院」という一般的なイメージとの間にずれがあり、制度の役割が分かりにくいという意見がありました 。
そこで、「口腔管理体制強化加算(口管強)」へと名称を変更し、「かかりつけ」という言葉に縛られず、より広くライフステージに応じた継続的な口腔管理(う蝕や歯周病の重症化予防、小児の口腔機能発達不全への対応、高齢者の口腔機能低下への対応など)を推進する体制を評価する基準へと刷新されました。これは、予防歯科や高齢化社会における口腔機能維持の重要性を国が重視していることの表れです。
主な変更点の概要
表1:主な施設基準の新旧対照表
| 旧基準 (Old Standard) | 状態 (Status) | 新基準 (New Standard(s)) | 主な焦点の変化 (Key Focus Change) |
| 歯科外来診療環境体制加算1 (外来環1) | 廃止 (Abolished) | 歯科外来診療医療安全対策加算1 (外安全1) | 医療安全、緊急時対応 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 (外感染1) | 院内感染防止策、設備 | ||
| かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (か強診) | 廃止/改定 (Abolished/Revised) | 口腔管理体制強化加算 (口管強) | 包括的口腔管理(小児・機能含む)、安全・感染対策、多職種連携 |
これらの新しい基準を満たすための具体的な要件を詳しく見ていきます。
A. 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
人員体制:
- 医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること(医科歯科併設の場合は歯科部門に配置)。
設備・連携
- 偶発症等、緊急時の対応に必要な体制(他の保険医療機関との連携体制を含む)が整備されていること。
- AED(自動体外式除細動器)、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セットなどが整備されていることが望ましい(口管強の要件と共通する部分が多い)。
体制・研修
- 医療安全対策に関する指針の整備、院内研修の実施など、十分な体制が整備されていること。
- 医療事故やインシデント(ヒヤリ・ハット)の報告・分析・改善を行う体制、または日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加・情報収集を行っていること。
掲示
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨を院内に掲示していること。
- 原則として、その掲示事項を自院のウェブサイトに掲載していること(令和7年5月31日までの経過措置あり。
B. 歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)
前提条件
- 「歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準(歯初診)」を届け出ていること。
人員体制
- 歯科医師が複数名配置、または歯科医師1名以上かつ、(歯科衛生士 または 院内感染防止対策に係る研修を受けた者)が1名以上配置されていること(外来環1時代より人員要件が緩和された可能性があります 。
- 院内感染管理者が配置されていること(院長でも可 )。
設備
- 標準的な感染防止設備(滅菌器など)に加え、口腔外バキュームを設置していること 10 (兵庫県保険医協会:
http://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2024/0415/100001.php)。患者ごとの器具交換・滅菌の徹底は歯初診の要件でもあります 17 (ジョブメドレーアカデミー:https://jm-academy.jp/contents/columns/m1_7860alkj)。
体制・研修
- 院内感染防止対策に関するマニュアルの整備、職員への研修実施など、十分な体制が整備されていること。
掲示
- 院内感染防止対策を実施している旨を院内に掲示していること。
- 原則として、その掲示事項を自院のウェブサイトに掲載していること。
C. 口腔管理体制強化加算(口管強)
口管強は、か強診の基準をベースに、多くの要件が追加・強化されています。
人員体制
- 歯科医師が複数名配置、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置。
実績要件(過去1年間)
- 歯周病安定期治療(SPT)または歯周病重症化予防治療(P重防)を合わせて30回以上算定。
- エナメル質初期う蝕管理料または根面う蝕管理料を合わせて12回以上算定(旧か強診の「初期う蝕・F局10回以上」から変更)。
- 歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症・低下症管理)、口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、歯科口腔リハビリテーション料3のいずれかを合わせて12回以上算定(小児関連が明確化)。
- 歯科訪問診療(1・2・3)の算定回数または連携先(歯援診1・2、在宅療養支援歯科病院)への依頼回数が合わせて5回以上、または、連携する別の訪問診療実施機関や地域の相談窓口と協議し、十分な訪問診療体制が確保されていること(体制確保の選択肢が追加)。
- 診療情報提供料または診療情報等連携共有料を合わせて5回以上算定。
研修要件
- 常勤歯科医師が、重症化予防(初期う蝕管理、根面う蝕管理、口腔機能管理を含む)、高齢者・小児の心身の特性、緊急時対応に関する適切な研修を修了していること(小児、初期う蝕・根面う蝕管理の研修が追加・必須化)。
※研修は日本歯科医師会(日歯)のE-systemなどで受講可能な場合があります。
連携・体制
- 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
- 歯科訪問診療を行う患者に対し、担当医をあらかじめ指定し、患者・家族に文書で説明する体制があること。
- 患者情報を共有する連携医療機関(特別の関係を除く)が5つ以上あること。
歯科医師の活動要件
- 担当歯科医師が、居宅療養管理指導の実績、地域ケア会議への出席、介護認定審査会委員経験、多職種連携会議への出席、在宅歯科関連の特定加算算定実績、在宅医療・介護研修受講、認知症対応力向上研修等の受講、福祉施設等での定期健診協力、自治体事業への協力、学校歯科医等への就任、歯科診療特別対応加算の算定実績などの項目のうち、3つ以上に該当すること(認知症、施設健診、自治体協力、学校歯科医などが追加)。
設備
- AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セットなどの緊急時対応設備。
- 歯科ユニットごとに、歯の切削時等に飛散する物質を吸引できる歯科用吸引装置(口腔外バキューム等)を設置していること。
掲示
- 院内掲示に加え、原則として自院のウェブサイトに関連事項を掲載していること。
口管強の要件チェックリスト(例)
口管強のように要件が多い基準については、以下のようなチェックリスト形式で自院の状況を確認すると良いでしょう。
表2:口腔管理体制強化加算(口管強) 要件チェックリスト(簡易版)
| カテゴリ | 主な要件 | か強診からの主な変更点 | 経過措置対象 (R7.5.31まで) | 対応状況/必要アクション |
| 人員 | 歯科医師複数名 or 歯科医師+歯科衛生士 各1名以上 | 変更なし | 対象外 | スタッフ構成を確認 |
| 実績 | SPT/P重防 ≥ 30回/年 | 変更なし | 対象外 | 実績を確認・集計 |
| 初期う蝕/根面う蝕管理 ≥ 12回/年 | 基準変更 (回数・内容) | 対象 (回数合算可) | 実績を確認・集計 | |
| 小児/口腔機能管理関連 ≥ 12回/年 | 小児関連の明確化 | 対象外 | 実績を確認・集計 | |
| 訪問診療 ≥ 5回/年 or 体制確保 | 体制確保の選択肢追加 | 対象 (回数合算可) | 実績確認 or 体制構築 | |
| 情報提供/連携共有 ≥ 5回/年 | 変更なし | 対象 (回数合算可) | 実績を確認・集計 | |
| 研修 | 重症化予防、高齢者・小児特性、緊急時対応、初期う蝕・根面う蝕管理 | 必須研修の追加 (小児・う蝕管理) | 対象外 | 必要研修の受講完了 |
| 連携 | 緊急時連携医療機関 | 変更なし | 対象外 | 連携先を確認・確保 |
| 連携医療機関 ≥ 5施設 | 具体的な施設数の明記 | 対象 (みなし認定) | 連携先を確認・確保 | |
| 活動 | 歯科医師が3項目以上該当 (認知症研修、学校歯科医等追加) | 該当項目の追加 | 一部対象 (特定加算実績) | 該当項目を確認・充足 |
| 設備 | 緊急時対応設備 (AED, O2等) | 変更なし | 対象外 | 設備を確認・整備 |
| ユニット毎の吸引装置 | 明確な要件化 | 対象外 | 設備を確認・整備 | |
| 掲示 | 院内掲示 + ウェブサイト掲載 (原則) | ウェブサイト掲載の義務化 | 対象 (ウェブサイト掲載) | ウェブサイト準備・掲載 |
注:これは簡易版です。必ず公式の告示・通知、チェックリストで全要件をご確認ください。
D. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準(歯初診)
歯初診は、外来環1や か強診の直接的な後継ではありませんが、外感染1の前提条件(厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf)であり、多くの加算の基礎となる重要な施設基準です。
- 主な要件:
- 口腔内で使用する機器等の患者ごとの交換や専用機器での洗浄・滅菌等、十分な院内感染防止対策。
- 感染症患者に対する診療体制の確保。
- 院内感染防止対策に係る研修を受講した常勤歯科医師の配置 。
- 院内感染対策に関する事項の院内掲示。
- 年1回の厚生局への実施状況報告。
- 原則として、ウェブサイトへの関連事項掲載。
- 届出: 様式2の6を用いて届け出ます。実績は不要です。
- 研修: 歯初診、外感染1、口管強の研修要件を同時に満たす研修コースも存在します。
要件充足に向けた考え方
新しい基準、特に口管強では、単に設備を揃えるだけでなく、研修による知識・技術の習得、日々の診療実績の積み重ね、マニュアル整備や院内体制の構築、そして多職種との連携といった、プロセスや継続的な取り組みがより重視されるようになっています。これは、付け焼き刃ではない、質の高い医療提供体制を評価しようという意図の表れと考えられます。
また、ウェブサイトへの掲示義務化は、医療DX推進の一環であり、患者への情報透明性を高める目的があります。
自院のウェブサイトがない場合は、原則として掲示義務の対象外となりますが、多くの基準で「原則」とされているため、今後の動向も注視が必要です。令和7年5月31日までの経過措置期間 を利用して、ウェブサイトの準備や改修を進めることが推奨されます。
これらの変化は、歯科医院に対して、臨床スキルだけでなく、運営管理能力、情報発信能力、継続的な学習姿勢を求めていると言えるでしょう。
5. 再提出(届出)の具体的な方法
経過措置の対象となっている歯科医院が、令和7年6月1日以降も外安全1、外感染1、口管強などを算定し続けるためには、令和7年5月31日までに再届出が必要です。ここでは、その具体的な手続きをステップごとに解説します。この手順は、新規にこれらの基準を届け出る場合にも基本的に共通します。
ステップ1:必要な届出様式の特定と入手
- 各施設基準には、それぞれ定められた届出様式があります。
- これらの様式は、自院の所在地を管轄する地方厚生(支)局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 主に必要となるのは、基本診療料または特掲診療料の共通の届出書と、各施設基準専用の添付書類です。
- 外安全1・外感染1: 様式4
- 口管強: 様式17の2
- 歯初診: 様式2の6
- 様式は全国共通が基本ですが、宛名などが異なる場合があるため、必ず管轄の厚生局のウェブサイトから入手してください。
ステップ2:施設基準届出チェックリストの活用
- 厚生労働省や各厚生局が提供している「施設基準届出チェックリスト」は、今回の改定で新設・変更された基準や、再届出が必要な基準を把握するのに役立ちます。
- どの基準を届け出る必要があるか、届出が完了したかをチェックすることで、届出漏れを防ぐことができます。
- このチェックリスト自体は、厚生局に提出する必要はありません。あくまで院内での確認用ツールです。
ステップ3:届出様式の記入
- 様式の各項目を正確に、漏れなく記入します。
過去の届出年月日が不明な場合
- 届出年月日の代わりに、その基準に基づく算定を開始した年月日(算定開始年月日)を記載し、その旨を(算定開始)のように付記することで対応可能です。算定開始年月日は、厚生局のウェブサイトに掲載されている「届出受理医療機関名簿」で確認できる場合があります。
口管強(様式17の2)の記入
- 旧か強診や歯援診(在宅療養支援歯科診療所)の届出状況を記載する欄があります。該当する場合は、受理番号や算定開始年月日などを指示に従って記入します。
- 経過措置期間中に実績要件などを「みなし認定」でクリアしている場合は、その旨が分かるように記載(または未記載でOKとされている項目も)します。
- 記載例(記入見本)が、歯科医師会や関連団体、コンサルティング会社などから提供されている場合もありますので、参考にすると良いでしょう。
ステップ4:添付書類の準備
- 施設基準によっては、届出様式に加えて添付書類が必要です。
- 特に、研修修了を証明する書類(研修修了証)は、外安全1、外感染1、口管強などで求められる重要な添付書類です。
修了者名、研修名、実施主体、修了日などが記載された一覧表形式でも認められる場合があります。 - その他、連携体制を示す書類や、院内マニュアルの概要などが必要となる場合もあります。各様式の注意書きや厚生局の指示を確認してください。
ステップ5:厚生局への提出
提出先:自院が所在する都府県を管轄する厚生局の事務所(または指導監査課) 。
提出方法:原則として郵送。一部、電子申請システムを利用できる場合もあります。担当厚生局にお問い合わせください。
提出部数: 添付書類を含め1部
控えの保管: 提出する書類一式のコピー(写し)を必ず自院で保管してください。これは、後日の確認や監査等に備えるためにも重要です。
郵送方法: 郵送事故を防ぎ、提出した証拠を残すため、追跡可能な方法(レターパック、簡易書留など)での郵送が強く推奨されます。厚生局は電話での到着確認に対応しない場合が多いです。
受付日と算定開始日: 郵送の場合、厚生局に書類が到着した日が受付日となります(消印日ではない)。受理されれば、原則として受理された月の翌月1日から算定可能ですが、月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日から算定できます。審査には通常2週間~1か月程度かかります。
押印: 令和3年2月以降、厚生局への届出様式への押印は原則不要となっています。
ステップ6:届出内容の変更・訂正
- 提出した書類に不備(記入漏れ、添付書類不足など)があった場合、厚生局から補正(訂正)を求められます。速やかに対応しましょう。
- 届出が受理された後で、人員の変更や設備の故障などにより施設基準を満たさなくなった場合、または届出区分が変更となった場合は、その事実が発生した翌月に変更の届出を行う義務があります。これを怠ると、不正請求とみなされるリスクがあります。
届出における心構え
施設基準の届出は、単なる事務手続きではなく、自院の医療提供体制が国の定める基準を満たしていることを公的に示す重要なプロセスです。特に今回の改定では、多くの医院で再届出が必要となります。
厚生局には多数の届出が集中するため、処理には時間がかかります。令和7年5月31日の期限ギリギリではなく、余裕を持ったスケジュールで準備・提出を進めることが肝要です。チェックリストの活用、追跡可能な郵送方法の選択、控えの確実な保管といった丁寧な管理が、スムーズな手続きと将来的なトラブルの回避につながります。
6. まとめと今後の注意点
令和6年度診療報酬改定は、歯科医院の施設基準に大きな変更をもたらしました。特に、従来の「外来環1」と「か強診」が廃止・再編され、「外安全1」「外感染1」「口管強」という新しい基準が登場した点は重要です。
令和6年3月31日時点で旧基準(外来環1・か強診)を届け出ていた歯科医院は、経過措置の対象となり、一定期間は新しい基準の一部を満たしているとみなされます。しかし、この経過措置は令和7年(2025年)5月31日に終了します。
令和7年6月1日以降も新しい基準(外安全1、外感染1、口管強)に基づく加算を算定し続けるためには、この令和7年5月31日までに、新しい基準の全ての要件を満たした上で、厚生局へ再届出を完了させる必要があります。
歯科医院が取るべきアクション
- 自院の状況確認: まず、令和6年3月31日時点で外来環1・か強診の届出があったかを確認し、経過措置の対象となるか把握してください。
- 新基準の理解: 算定を目指す新しい施設基準(外安全1、外感染1、口管強など)の具体的な要件(人員、設備、実績、研修、連携、掲示など)を、厚生労働省の告示・通知や厚生局の資料、本記事などを参考に、正確に理解してください。
- 計画的な準備: 経過措置期間を有効に活用し、不足している要件(特に研修受講、設備導入、院内体制整備、ウェブサイトへの掲示準備など)を計画的に満たしていく必要があります。
- 早期の再届出: 必要な様式と添付書類を準備し、記入漏れや不備がないか確認の上、令和7年5月31日の期限に十分間に合うよう、早めに管轄の厚生局へ郵送(追跡可能な方法で)してください。控えの保管も忘れずに行いましょう。
- ウェブサイト対応: 多くの施設基準で原則義務化されたウェブサイトへの掲示について、令和7年5月31日までに対応できるよう準備を進めてください。

今後の注意点
- 公式情報の確認: 診療報酬改定に関する情報は、厚生労働省や地方厚生(支)局から、疑義解釈資料(Q&A)や事務連絡といった形で追加情報が出されることがあります。常に最新の公式情報を確認する習慣が重要です。
- 研修情報の確認: 必要な研修については、日本歯科医師会や地域の歯科医師会、関連学会などが提供する情報を確認し、計画的に受講してください。
- 様式・手続きの変更: 厚生局のウェブサイトなどで、届出様式や手続きに関する変更がないか、定期的に確認することをお勧めします。
今回の施設基準の見直しは、歯科医院にとって対応すべき課題が多いことも事実ですが、これを機に自院の医療安全体制、感染防止対策、そして患者さん一人ひとりの口腔の健康を生涯にわたって支える体制を見直し、強化する良い機会と捉えることもできます。基準への適合は、質の高い歯科医療を提供している証となり、患者さんからの信頼にも繋がるでしょう。本記事が、その一助となれば幸いです。
基本的な用語の確認
- 施設基準 (しせつきじゅん – Shisetsu Kijun): 特定の診療報酬(特に加算)を算定するために、医療機関が満たすべき人員、設備、体制などの基準。品質の高い医療提供体制を評価するものです。
- 経過措置 (けいかそち – Keika Sochi): 制度変更時に、旧制度下で要件を満たしていた医療機関が、直ちに不利益を被らないように設けられる移行期間や猶予措置。
- 算定 (さんてい – Santei): 診療報酬点数表に基づいて、行った医療行為に対応する点数を計算し、請求すること。施設基準を満たして届け出た加算を請求に含めることを指します。
- 厚生局 (こうせいきょく – Kōseikyoku): 厚生労働省の地方支分部局で、各地域(例:関東信越、東海北陸など)の保険医療機関の指導・監督、施設基準の届出受理などを行います。
- 届出 (とどけで – Todokede): 施設基準などを満たしていることを、厚生局に正式に書類で知らせる手続き。受理されて初めて、該当する診療報酬を算定できます。「再届出(さいとどけで – Sai Todokede)」は、基準変更などに伴い、改めて届け出ることです。